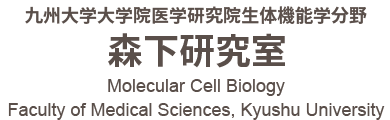高吉さん(医学部生命科学科3年)の研究室配属感想文が学科Webサイトに掲載されました
2025年7月から3年次研究室配属として森下研究室に加わってくれている医学部生命科学科3年の高吉瞭太さんの研究生活の感想が、医学科・生命科学科のWebサイトに掲載されました(以下抜粋)。
研究室配属感想文
医学部生命科学科3年 高吉 瞭太
私は研究室配属において、生体機能学分野で約1か月間お世話になりました。この教室では、細胞内で起こる大規模な分解現象、その詳細なメカニズムや関連疾患の治療法についての研究を行っています。またゼブラフィッシュという小型魚類をモデル動物として用いているのも特徴で、マウスなど他の実験動物とは異なる実験法や観察を行うことができます。
一か月間にわたり行った研究の目的は、ゼブラフィッシュ水晶体内に存在する mRNA の寿命の可視化です。水晶体の線維細胞では分化に伴い分解現象が見られますが、その時水晶体特異的な mRNA は非特異的な mRNA より安定性が高く分解されにくいという仮説を検証しました。cDNA の一部を観察に適したものに付け替えるコンストラクションや、そこから mRNA を PCR や転写で精製する必要があり、それらを自分で行う中で分子生物学的手法の基礎を学び実践することができました。さらに、得られた mRNA を受精卵にインジェクションする操作も行いましたが、器用さと慣れが必要な作業であるため自分にはとても難しく、何十個もこなしている研究室の方々を見て驚くばかりでした。
また配属期間では毎日の実験のほか、研究室内で週1回行われるミーティングにも参加しました。研究内容や論文抄読等の発表と、それに続く質問が主な内容です。先生方や先輩方の研究自分の初歩的な質問にも丁寧に答えて下さりと、今後の学生生活に活かせるような貴重な経験を得ることができたと感じています。
この実験や抄読会を行う中で最も実感したのは、出会う用語や現象を表面的に受け止めるだけでなく、「なぜこのようなことが起こるのだろう」「これはどういう意味だろう」といった疑問を持ち続けることの重要性です。どんなに初歩的でも、あるいは一見実験と関係のなさそうなことであっても、浮かんだ疑問を大切にする姿勢が研究者に欠かせないことを学びました。実験を行う中で PCR、制限酵素、形質転換、分光光度計といった用語が何度も登場します。これらは過去の講義で聞いたことのある単語であり、自分もおおよそ理解しているつもりでした。しかし実験で問題が発生したときに、そもそも正常に進行したときに何がどのような反応を起こしているのかまでは理解できておらず、何が間違っているのか見当もつきませんでした。この経験を通じて、自分が「理解しているつもり」になっていた内容は、実際には説明文を暗記していただけで、本質的なところまで見ていなかったことに気が付きました。現在は表面的な理解にとどまらず、用語の意味を咀嚼して、背後にある原理を追い続けることを意識しています。
研究室の皆様のおかげで気づきと学びにあふれた、密度の高い一か月を過ごすことができました。お忙しい中丁寧に指導していただき、本当にありがとうございました。